賃貸経営にとって出口戦略はとても重要なポイントの一つです。
賃貸経営における「出口戦略」とは「所有している物件を売却するか?一度、更地にしてから立て直すか?ずっと持ち続けるか?」などを検討し、最も適切な選択を判断することです。
これから物件を購入しようかと考えている不動産投資の初心者にとってはこのように思う人もいるかもしれません。
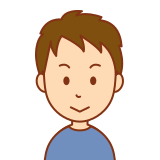
まだ物件を購入してもいないのに売却のことを考えるのは、さすがに気が早すぎるなぁ。
まずは安定した家賃収入が確保できる物件を探すことに専念しよう。
ですが、実際の出口戦略は「物件を購入する前」からあらゆることを想定しなければいけません。
ちょっと大袈裟に聞こえるかも知れませんが、売却を想定しない物件購入には大きなリスクが存在します。
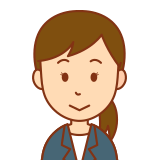
少し気が早いように感じるかもしれませんが、物件を購入するタイミングでしっかりと出口戦略を考えておかなければ、取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。
今回は「賃貸経営における出口戦略の考え方」についてまとめてみました。
既に投資用物件を保有している人だけでは無く、これから投資用物件の購入を検討している人にとっても重要なポイントになる内容ですので、是非、最後まで読んで頂ければと思います。
- 出口戦略の考え方を理解し売却のタイミングを見誤りたくない人
- 出口戦略の注意点を理解し適切なゴールを目指したい人
出口戦略の重要性は?

物件ごとの投資結果が「成功だったか?」「失敗だったか?」を評価するには「最終的にいくらで物件を売却できたか?」によって判断します。
もし物件を保有している間、空室率も低く十分なキャッシュフローが達成できていても、売却価格が想定以上に低ければ、その事業は失敗かもしれません。
まだ物件の購入前だとしても、最低限の出口戦略は意識するようにしましょう。
出口戦略の種類
出口戦略と聞くと「いつ売却するか?」「いくらで売却するか?」を考えるのが一般的ですが、賃貸経営でにおける出口戦略には以下のような方法があります。
- 物件をそのまま売却する
- 物件を空室を埋めて満室にしてから売却する
- 物件の修繕やリフォームをしてから売却する
- 物件を解体し更地にしてから売却する
- 物件を解体し駐車場やコインランドリーなどで活用する
- 物件を解体し新しく建て替えてから売却する
- 物件を解体し新しく建て替えてから再び自身で賃貸経営する
- そのまま持ち続ける(賃貸経営を継続する)
勿論、適切に分析できているのであれば「敢えて売却は考えずそのまま持ち続ける」という選択肢も悪くないと思います。

建物構造による選択肢の違い
例えば、戸建てや一棟アパートであれば、家主(所有者)に物件自体を解体する権利があるため、更地にしたり、立て直したりとさまざまな選択肢があります。
一方、分譲マンションの1区分しか所有していない場合、関係者の合意が無ければ取り壊しなどはできないため、室内を多少リフォームすることはできますが、基本的には保有し続けるか売却するかの2択に絞られるはずです。戸建や一棟アパートと比べると選べる選択肢はかなり狭くなってしまいます。

意思決定のポイント
投資用物件の出口戦略を考えた場合、意識しなければいけないポイントが沢山あります。
株式投資などの場合だと「銘柄をいくらで購入して、いくらで売却できたか?」が全てです。
もし利益があった場合は所得税(配当所得)が掛かりますが、所得税率も一律で20%程なので、それ程、複雑ではありません。他にも株式売買に伴う手数料などが掛かりますが、正直、微々たるものですし、
一方、賃貸経営の場合はさまざまな費用が関わってくるため、しっかりと整理しておかないと「得だと思って売却したのに実は損していた…」なんてことにもなりかねません。具体的には以下のような費用が関わってきます。
- 物件の購入価格および売却価格に関わる費用
- 仲介手数料、収入印紙代、銀行手数料など
- 抵当権抹消費用、司法書士手数料など
- 保有期間中の家賃収入
- ※これまでの実績金額
- 保有し続けることによって得られるであろう見込み収入
- ※将来の予想額
- 保有期間中の経費
- 管理費、修繕積立費、広告費、固定資産税など
- 減価償却費、金融機関への融資返済金利など
- 不動産所得に対する所得税、住民税
- 法人設立に伴う初期費用、運営費用
- 顧問税理士費用、法人住民税
- 解体費用、リフォーム費用
とても項目が多くて挫けそうになりますが…
これらの全ての金額を換算することで、その物件によるの経営が「成功したか?」「失敗したか?」を評価します。
ただ「損失が出てしまうからずっと保有するしかない」と考えるのも軽率です。
認めたくない気持ちも分かりますが、投資をする以上、損失が出るのは仕方の無いことです。
自体が改善される根拠も無く、ただ頑なに保有し続けるのはただの「塩漬け状態」です。
例え失敗してしまったとしても、その原因をしっかりと分析し次に繋げるべきです。
売却を判断する場合は、売却することにより一括で手に入る収益と賃貸を継続し家賃収入を積み重ねることによる収益を天秤に掛けて「どの選択が正しいのか?」を見極めることが必要です。
物件売却のメリット
投資用物件を売却するメリットは当然ながら纏まったキャッシュが手に入ることです。
手元にまとまった資金があれば新規物件を購入するための軍資金になりますし、新規物件の購入により資産の若返りも期待できます。
勿論、立地や収益性によりどの物件を売却するかの判断が変わりますが、自分で判断して優良物件だけを手元に残すことができれば資産の棚卸しと言う意味では大きなメリットです。
勿論、売却した資金には手を付けずに、そのまま老後資金として保有し続けるのも一つです。

売却に伴う注意点

株式投資であれば、売却予定額をもとに「本当に売却するべきか?」「もう少し保有し続けるべきか?」を考えるくらいなので比較的シンプルに判断できます。
ですが、投資用物件を売却する場合は「この価格で満足できるか?」以外にも、たくさん考慮するポイントがあります。
ローンが返済できるか?
まず、最初に思いつくのが「金融機関へのローンを返済できるか?」です。
投資用物件を購入したものの、想定通りのキャッシュフローが見込めないことは良くある話です。
販売会社の営業は「不確実なシュミレーション」をもとに、将来のキャッシュフローを提示してきますが、現実はそう甘くありません。
つまり、巧みな営業トークに騙されてしまったパターンです。
この場合、すぐにでも売却して損失を最小限の抑えたいというのが本音かもしれません。ですが、金融機関から融資を受けている場合、購入の初期段階では利息部分の返済に占める割合が多く、ほとんど元金が減っていおらず、仮に売却できたとしても、大きなマイナスになってしまう場合もあります。
返済を進めることで、元金部分に占める割合が増えていきますが「判断を誤って購入してしまった物件」の場合、無駄に長い期間物件を保有すれことで、むしろ状況が悪化するかもしれません。
この辺りの判断は難しいですが、感情面での損得だけで無く「保有によるリスク」と「売却による損失」を見極める必要があります。

譲渡所得の仕組みを理解する
出口戦略を考える時、譲渡所得を意識することはかなり重要です。
売却によって譲渡所得が発生する場合は、物件の所有期間によって所得税率や住民税率が大きく変わります。
譲渡所得とは物件を売却することによって得られる収入です。投資用物件における譲渡所得および譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
- 譲渡所得=譲渡価格(売却価格)-簿価(帳簿価額)
- 簿価(帳簿価額)=購入価格-既に経費計上した減価償却費分
- 譲渡所得税=課税譲渡所得×譲渡所得税の税率
重要なポイントは譲渡所得は譲渡価格(売却価格)から購入価格を差し引くのでは無く、簿価(帳簿価額)を差し引くということです。
簿価(帳簿価額)とは「購入価格から減価償却費分を差し引いた帳簿上の価額」のことです。
短期譲渡所得と長期譲渡所得
譲渡所得税の税率は物件の保有期間によって、以下の2種類に区別されます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率の違い| 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | |
|---|---|---|
| 所有期間 | 所有期間5年以下 | 所有期間5年超 |
| 所得税 | 30.63% | 15.315% |
| 住民税 | 9% | 5% |
| 合計 | 39.63% | 20.315% |
保有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、長期譲渡所得と比べて約2倍の税金が課せられてしまうため注意が必要です。

法人設立による節税対策
上記の通り、個人名義での所有物件だと譲渡所得税が大きな負担になりますが、法人名義で所有物件であれば、売買益に対する所得税を軽減できます。
その場合、途中で個人名義から法人名義に名義変更するのは難しいため、購入するタイミングで法人を設立して最初から法人名義で物件を購入する必要があります。

より高値で売却するには
物件の売却を検討する場合「少しでも高値で売却する方法は無いか?」を考えます。例えば、以下のようなことが挙げられます。
空室を埋めてから売りに出す
投資用物件の市場価格は積算価格や収益還元法によって計算されますが、金融機関からの評価としては「現時点での稼働率」もとても重要ですし、空室が一つでもあると、それを理由に値下げ交渉されることもあります。
可能な限り空室は埋めた状態で売りに出す方が高値で売却できる可能性が高くなります。

1部屋辺りの家賃収入を増やす
空室率同様、一部屋辺りの賃料も市場価格を決める上で大切な指数になります。
販売図面などには販売価格が一番大きく掲載されますが、投資用物件の場合、どうしても表面利回りは注目されてしまいます。
もし、近い将来、物件を売却することを想定している場合は、安易に賃料を下げて入居付けするのでは無く、多少、広告費を高めにしてでも家賃を少し高めに設定する方が販売価格を大きく見せることができます。
勿論、市場価格の平均と比較し余りにも割高な賃料を設定しても、投資家相手には直ぐに見破られてしまいますが、ある程度は高めに家賃設定した方が販売価格を維持する根拠になるはずです。
物件自体の品質を高める
物件自体の品質を高めるには以下のような方法が考えられます。
- エントランスや共用部分を綺麗に掃除する
- ニーズに適応したリフォームやリノベーションをする
- 大規模修繕工事をする
まずエントランスや共有部分の掃除は徹底的に綺麗に掃除するべきです。
特に購入希望者が訪れた際、すぐに目に付くような箇所は重点的に掃除しておくことで印象も変わります。
何より対してコストも掛からないため、やらない理由がありません。
一方、リフォームやリノベーションについては、本当に需要があるのかしっかり戦略を立てて慎重に取り組む必要があります。
「○○のような間取りが良いはず」と個人の思い込みで誤った対応をすればただの無駄金ですし、仮に工事の方針が正しかったとしても、期待できる販売価格の上昇以上のコストを掛けても意味がありません。
「ただの自己満足」にならないように費用対効果を考えた対策が必要です。
また、大規模修繕工事についても「適切な時期」があるため安易に進めると失敗します。
知り合いの工事会社など、低コストで対応してくれる業者などがいる場合は、付加価値を高めるために工事を実施するのもありですが、こちらも費用対効果が明確に期待できないのであれば、むしろ「大規模修繕工事は実施せずに、その分、値下げ交渉に応じる」方がリスクが少ないです。
また、日頃から修繕履歴を丁寧に記録することで、現状の物件価値を客観的に示せるようになります。
売却時の市場の動向を把握する

物件を売却する場合、その時々の景気動向により売却価格が大きく変動します。
極端な話、不動産バブルのような時代であれば、かなり割高な売却価格が期待できるかもしれません。一方、不景気であったり、不動産自体の価値が低減してしまっていれば、市場価格は低くなってしまいます。
今後、日本はインフレ経済を目指しています。残念ながら、今のところ、インフレ経済になることを期待できるような話題はありませんが、もし、物価が上昇すれば、売却できる価格の高くなるかもしれません。
次の購入者に融資が下りるかがポイント
「物件を売却をする」ということは、当然のことですが「その物件を購入する人がいる」ということになります。
例えば、区分マンションの場合、ワンルームマンションとファミリーマンションとでは「次の購入者層」にも違いがあります。ファミリーマンションの場合は住居用として家族で住むために購入される場合もありますが、ワンルームマンションの場合は個人の住居用として購入する可能性は低く、次の購入希望者も投資目的として購入するはずです。
住居用と投資用とでは利用できるローンの種類も違うため、金融機関の融資姿勢によっては、次の購入者が限定されてしまい値崩れの幅にも大きな違いが出てきます。
買い手側が融資を付けることができれば問題ありませんが、融資がスムーズに決まらなければ、売り手側にとっても大きな影響を与えます。
金融機関の融資動向に注目する
例えば、2018年〜2019年頃にかけて「かぼちゃの馬車の問題(スルガ銀行の不正融資問題)」などの影響により、個人への融資のハードルが一気に高くなってしまいました。その他にも、景気変動などにより金融機関の融資方針が変わってしまうと売買価格に大きな影響を与えることもあるはずです。
「融資が下りない」ということは「購入したくても購入できない人」が増えてくるため、自然と販売価格も低下傾向になります。
なお、金融機関からの融資の返済期間は、基本的には減価償却期間の範囲内であることが多いため、築年数が古い物件の場合は、売却できる(できる可能性が残っている)タイムリミットを意識する必要があります。
地域ごとに変わる融資の基準を把握する
「不動産業界の常識」と「地域ごとの常識」が異なることは意外と多いです。
例えば、一般的に以下のような物件には融資が付きにくいと言われます。
- 法定耐用年数を超過した古い物件
- 容積率オーバーのような違法物件や既存不適格物件
法定耐用年数が超過した物件は老朽化してしまっているので金融機関としても担保としての評価額が出しずらいですし、容積率オーバーのような違法物件や既存不適格物件にはコンプライアンス的にも積極的な融資が難しいとされます。
つまり、これらの物件は「利回りは高いものの次の売却先が見つからず出口戦略で苦労する」と考えられる訳です。
ですが、実は関西圏では意外と融資が下りることもあります。
これは「金融機関ごとの融資姿勢」にも影響しますし「関西(主に大阪府)では容積率オーバーの物件も一定数あり全ての違法物件の融資を停止すると融資先が限られてしまう」という地域ならではの課題があるからです。
あくまで金融機関側の考え方であるため、将来的に方針転換もあるかもしれませんが「○○だから融資は下りない」と諦めるのは勿体ないかもしれません。
融資の基準は地域によっても変わるため「自分が物件を所有したい地域ではどうなのか?」を把握することで、購入対象の選択肢が増えることもありそうです。
出口戦略で失敗しないためには?

出口戦略で失敗をしない方法を考える上で重要なのは「投資用物件を購入する前にだけ可能な対策」と「投資用物件を購入した後から可能な対策」とは分けて考えることです。
物件購入の前後で打てる対策が変わる
ここまでのさまざまな出口戦略の注意点などを解説してきましたが、以下のように、有効な出口戦略は投資用物件購入の前後で大きく変わることが分かると思います。
- 投資用物件を購入する前にだけ可能な対策
- 建物の種類(分譲マンションか?1等アパートか?戸建てか?)を考慮する
- 建物の構造(ワンルームか?ファミリー向けか?)を考慮する
- 「次の購入希望者にも融資が下りるか?」を考慮する
- 地域ごとに変わる融資姿勢を把握して考慮する
- 投資用物件を購入した後から可能な対策
- 空室を埋める
- 1部屋ごとの賃料を上げる(表面利回りを大きくする)
- 物件の品質向上(掃除、修繕など)に取り組む
- 短期譲渡所得と長期譲渡所得を考慮する
こうして見てみると「投資用物件を購入した後から可能な対策」には限りがあり、やはり「投資用物件を購入する前にだけ可能な対策」を把握した上で事前準備に取り掛かる必要がありそうです。
高値で購入しないことが何よりも大切
出口戦略だけに関わりませんが、賃貸経営全体として一番大切なのは「正しい物件を適切な価格で購入する」ことです。
勿論、建物の種類や構造、金融機関の融資動向なども大切ではありますが、単純に「購入金額を上回る価格で売却する」ことができれば賃貸経営で失敗する可能性も極限まで減らすことができます。
勿論、全ての投資家が同じことを考えているはずなので、そう簡単に実現することはできませんが、大きく値崩れしないような割安価格で物件を購入することが、何よりも重要な解決策だと言えます。
ずっと所有するのではダメなのか?

それでは、賃貸経営が順調な場合、その物件をずっとそのまま保有しておく訳にはいけないのでしょうか。
勿論、保有してからずっと高い利回りを維持し続けられる物件の場合は、その利回りが続く限り、保有し続ける方が良いはずです。
ですが、どこかのタイミングで必ず利回りは下がってしまいますし、減価償却期間が迫ってくると、購入者側の融資が困難になることもあるため、やはりある程度は「売却に対する意識」は持ち続けなければいけないと思います。
それに、今が順調だからと言って、この先もずっと順調かどうかはまた別の話です。
誰だって高値で売却できることが一番良いですが、空室が発生したり賃貸価格が減り続けると、その分資産価値が低くなってしまうため、その分売却価格にも影響を与えます。
ただ、いずれにしても自分の希望に近い価格で売却できるよう慎重に判断できる状況を維持することが重要です。「資金繰りが悪くなったため多少安くでも良いから今すぐ現金が必要になる」という状況になってしまうと、はやり足元を見られてしまいます。
20年後、30年後の売買価格のシュミレーションがどれ程の精度になるかは家主(投資家)の腕や経験に左右されます。物件の管理状況にも影響するため管理会社に物件管理を依頼している場合はなおさら不透明になります。
ただ、売却を「全く意識しない」のはその分機会損失を招いてしまいます。
過剰に意識し過ぎる必要は無いかもしれませんが、すぐに売却しないとしても情報収集する姿勢は持っておくべきますし、日頃から所有物件に対して、どの程度の流動性が見込めるのかを把握しておくことは安心感に繋がります。
ライフステージごとに最良の方法は変わりますが、どんなタイミングでもなるべく自分の選べる選択肢を多く持っておくことが精神的にも投資的にも大切なんだと思いました。




コメント