皆さんはマンションを購入したり、賃貸契約を結ぶ時、どの部屋を選びたいですか?
「部屋が空いていればどこの部屋でも良い」という人もいるかもしれませんが、もし複数の部屋が選択できる場合は何か判断基準を持っておいた方が決めやすいと思います。
マンションはどこの部屋が人気?
マンションの部屋の種類は大きく分けると以下の4種類に分けられると思います。
- 部屋の階数
- 高層階、最上階
- 中層階、低層階
- 1階
- 部屋の位置
- 中部屋
- 角部屋
基本的には高層階や最上階、角部屋に人気が集まりそうですが、販売会社側としても人気が偏らないように販売価格に差を付けています。
基本的には販売価格や賃料は部屋の広さに比例して決まりますが、高層階にいけばいく程、金額は高くなるため、価格設定によっては中層階の方に人気が集中することもあります。
ちなみに僕が住んでいるのは6階建てマンションの1階の角部屋です。もともとはモデルルームとして使われていた部屋を比較的安くで購入できたので数年前からそこに住んでいます。
勿論、高層マンションの高層階にも憧れはありますが、利便性や経済的な問題を天秤に掛けると、1階の部屋で良かったと思っています。
部屋ごとの特徴について
部屋ごとの特徴について簡単にまとめてみました。
やっぱりできれば最上階に住みたい?
高層階や最上階の特徴としてはこのようなものが考えられます。
展望が良い
高層階、最上階の特徴としてはやっぱり展望が良いことが挙げられます。
高層マンションの場合、周りに同じ高さの障害物が無ければ街を一望することだってできます。
ただしここ最近は大阪や神戸でも次々とタワーマンションが乱立されているため、周りに同じようなタワーマンションやオフィスビルが建てられてしまったら、せっかくの展望が台無しになってしまいます。
少し視界が狭くなる位であれば我慢できますが、自分のマンションの真隣により高層のマンションができてしまった場合、今までは一望できていた素敵な景色が障害物によって邪魔されてしまう可能性もあります。
プライバシーが確保しやすい
周りに同じ高さの建物があると、角度によっては少し視線が気になったりするかもしれません。
ですが、高層階の場合は、周りに建物が無いことが多いため、視線を気にする必要はありません。
「洗濯物を見られる心配が無い」ことも魅力の一つかもしれませんが、高層階の場合、落下の危険性から、そもそも洗濯物を外に干せない場合もあるため、事前に確認が必要です。
冷房が効きにくい
マンションの向きにも寄りますが、高層階になるとその分、遮る障害物が無いため、日当たりは良いです。
ただし、夏場は日当たりが良すぎるため室内が暑くなり過ぎてしまいます。最近では遮熱効果が高い窓ガラスが採用しているマンションも多いですが、それでもやっぱり暑くなってしまいます。
一般的には「日当たりが良いのは南向き」と言われますが、タワーマンションの高層階の場合は南向きだと日当たりが良すぎて熱がこもってしまうため、敢えて北向きを選ぶ人もいます。
エレベータの待ち時間が長くなる
大規模マンションの場合はエレベータが複数設置されていますし、タワーマンションの場合は高層階用と低層階用でエレベータが分かれていますが、それでもやっぱりエレベータの待ち時間は大きな問題です。
特に朝の出勤時などは混み合うことが多いため、エレベータの待ち時間をしっかりと通勤時間として想定しておかなければ遅刻してしまいそうです。
また普段は余り意識する必要はありませんが、地震などによって、万が一、エレベータが停止してしまった場合は階段を利用して移動しなければいけません。
とにかく販売価格が高い
後、何と言っても高層階や最上階の販売価格は高額になります。
低層マンションであればそれ程大きく変わらないこともありますが、タワーマンションの場合は上階になればなる程、販売価格は上がってしまいます。
なお、タワーマンションの価格の仕組みについては以下の記事でもう少し詳しく説明しています。

中部屋よりも角部屋が良い?
高層階と同様、角部屋にも根強い人気があります。角部屋の特徴には以下のようなものがあります。
視界が広く開放感がある
角部屋はバルコニーや展望が2面に面しているため、日当たりや通気性も良く、視界が広く開放感があるのが特徴です。
また、マンションの中で角部屋にだけ小窓が付いていることも多いです。マンションの場合、浴室に小窓が付いていないことも多いですが、角部屋にだけは浴室にも小窓が付いていることもあり、この辺りも嬉しいポイントです。
外部からの影響を受けやすい?
角部屋や中部屋に比べて、体部と面している面積が大きいです。
そのため、以下の項目などで中部屋以上に影響を受けてしまいます。
- 室内の温度(夏は暑く冬は寒い)
- 騒音(外の騒音が聞こえやすい)
外の環境に室内の温度が影響を受けてしまうということは、その分、冷暖房費が高くなってしまいます。角部屋は人気が高いですが、意外とデメリットもあるんですね。
角部屋は中部屋よりも割だけになる
角部屋は中部屋と比べ販売価格は高くなります。その理由には主に以下のようなことが考えられます。
- マンションごとに確保できる数に限りがあるため希少性が高い
- 中部屋よりも室内面積が広い
- 中部屋よりも窓が多いため施工費が掛かる
モデルルームなどで価格表などを見てみると、中部屋よりも角部屋の方が販売価格が高いことがひと目で分かりますが、それでも角部屋の人気は高いと思います。
1階は人気が無い?
最近の新築マンションには1階が無いマンションも多く見られます。
駐車場として活用したり、豪華なエントランスにするためにもともと1階部分を分譲しないマンションも増えてきています。
セキュリティ面での不安は大きい
セキュリティのことを考えると、やはり低層階の方がリスクが高いと言われます。
ただ最近のマンションではセキュリティ意識も高いため、ポイントとなる箇所に監視カメラが備え付けられていたり、簡単には部外者が侵入できないような作りになっていることが多いため、個人的には、それ程、セキュリティ面が脆弱だとは感じません。
コストパフォーマンスは意外と良い
セキュリティ面での心配からかどうしても1階部分は人気が劣ることが多いですが、その分、マンションによっては、専用庭が備えられていたりと、スペースを広く活用することができます。
専用庭の手入れは何かと大変だったりもしますが。。。
販売価格で考えると、1階が一番安いこともありますし、有効スペースが広い分、2階以上のフロアよりやや高くなってしまうこともありますが、一般的に他の階と比べてコストパフォーマンスが優れていることが多いです。
低層階は水圧が高い?
最近のマンションではほとんど影響は無いと思いますが、意外に知られていないメリットとして水圧が高いことが挙げられます。
一般的に給水設備(高架水槽)はマンションの屋上に設置されています。
なので低層階の方が水圧が高くなり、上層階と比べるとシャワーの出が良くなります。
実は余り知られていないその他の仕組み
部屋の種類ごとの特徴をまとめてみましたが、それ以外にも余り知られていない豆知識があります。
管理費・修繕積立費は階数とは関係無い?
マンションの販売価格は高層階になればなる程高くなります。
ですが、管理費や修繕積立費は床面積に比例することが多く、一般的には高層階だからといって割高になることはありません。
現実問題としては高層階になればなるほど修繕工事やエレベータのメンテナンスなどの維持費がかさむものですが、この辺りが低層階と変わらないのは嬉しいポイントだと言えます。
省エネ効果が高いのは中部屋?
省エネ効果を考えると、もっとも経済的なのは角部屋でも無く最上階でも無く、真ん中に位置する中部屋です。
ちなみに一般的に人気とされている最上階や角部屋と比べると、真ん中の方が周囲を居室に囲まれているため冷暖房の利用が抑えられ省エネ効果が高いです。
階数や方角、また上下左右の部屋のエアコンの利用具合にも寄りますが、角部屋最上階の部屋と比べると倍以上の省エネ効果を期待できることもあるそうです。
販売価格は1階ごとに変わる訳では無い?
マンションの販売価格は高層階になればなる程高くなります。
ですが、それは必ずしも階数が1階違うたびに、価格が変わる訳ではありません。
勿論、1階ごとに細かく価格設定がされていることもありますが、大規模なマンションの場合は「10階〜15階までは◯◯万円」というふうに複数階ごとに価格設定がされていることもあります。
仮に10階〜15階までが同じ価格なのであれば、どうせだったら15階を購入したいと考える人が多いと思います。このような細かい情報はインターネットで調べるだけでは中々手に入りにくいので、実際に販売会社やモデルルームで話を聞いた方が分かりやすいです。
タワーマンション高層階は相続税対策になる
タワーマンションの高層階は相続税対策に有効です。
相続税の計算方法は不動産の場合、固定資産税評価額が基準になります。その固定資産税評価額は各区分マンションの専有面積によって決まるため、高層階でも低層階でも同じになります。
実際の販売価格では高層階と低層階では大きな価格差がありますが、固定資産税評価額としては専有面積が同じであれば、高層階でも低層階でも同じになります。つまり高層階になればなる程、相続税対策になる訳です。
2018年から固定資産税評価額の計算方法が見直されはしましたが、実はそれ程影響はありません。
これからも法改正があるかもしれませんが、タワーマンションの高層階は相続税対策として引き続き有効な方法だと言えます。
相続税対策については以下の記事でもう少し詳しく説明しています。

自分にあった部屋が一番良い
これまで部屋の種類ごとの特徴についてまとめてきましたが、僕が個人的に意識していることをまとめてみます。
新築プレミアムは認識しておく
当然のことですが、新築物件は中古マンションに比べて価格が割高になります。
築年数が浅いことも一つの理由ですが、一番の理由は「新築である」からです。
いわゆる新築プレミアムと言うヤツですね。
ただ、最近では中古マンションの販売価格も高騰していて、一概に「新築=高い」とは言い切れなくなっています。
どちらを選ぶかはそれぞれの価値観によりますが、新築マンションの場合は、その分、実態以上に値段が高くなることは認識しておかなくてはいけません。

100万円をバカにしてはいけない
地域にもよりますが、関西で新築マンションを購入するには、やはり3,000万円〜4,000万円程の価格になることが一般的です。それに比べて販売手数料やその他の諸費用などで100万円単位のお金が必要になります。
そうなると人はこのように考えてしまうものです。
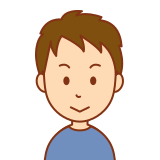
100万円くらいなら高くなっても余り変わらないよね。

一生に一度の買い物なのでケチケチしたく無いわ。
少し高いけど大きめの部屋にしましょう。
確かに3,000万円〜4,000万円程の大金の前では100万円という金額は誤差の範囲なのかもしれません。ですが、100万円を35年ローン(金利1.5%)で返済すると月々の返済額は3,000円程増えてしまいます。35年間、3,000円分の支払いが過程を圧迫するのです。
本当に必要であれば、多少高くなったとしても条件を満たすべきかもしれませんが、大金を前にして金銭感覚を麻痺させないように注意が必要です。
金銭感覚を麻痺させるのは販売担当(営業)の巧妙なテクニックです。
販売価格は需要と供給で決まる
人気の部屋にはそれ相応の販売価格が設定されます。
結局は需要と供給のバランスで販売価格は決まる訳なんですね。
タイミングによっては、運良く割安物件を購入できる可能性もありますが、それを意識することで、返って選択肢の幅を減らしてしまうこともあるでしょう。
それぞれの部屋の特徴を理解した上で、自分にあった部屋を探すことが一番良いと思います。
納得できればそれで良い
人それぞれ好みや必要となる条件は違いますが、結局は自分にあった部屋を見つけることが一番大切です。つまり「こんな部屋は選ぶべきでは無い」というものも特に無いと思います。
自分や家族が納得できる部屋であれば問題ありません。
現実的な返済計画を建てて、可能な範囲でやりくりしたら良いと思います。



コメント